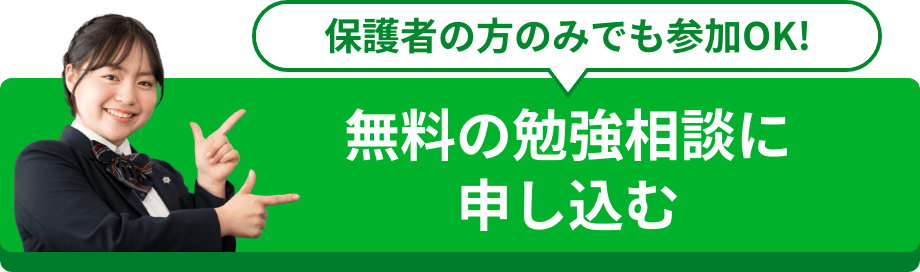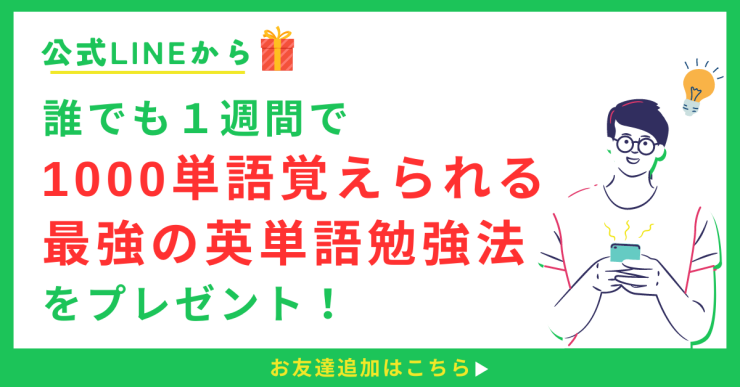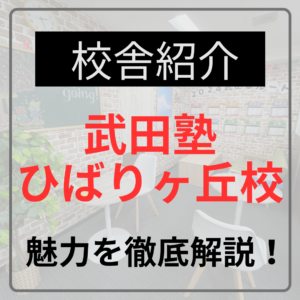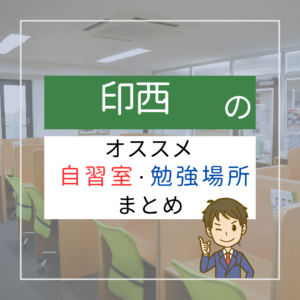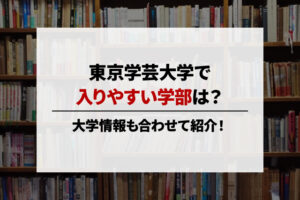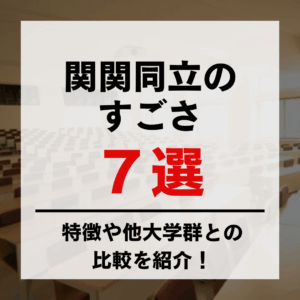武田塾10校舎 統括責任者(練馬校/田無校/ひばりヶ丘校/東久留米校/拝島校/入間校/小山校/草津校/滋賀守山校/滋賀彦根校)
1993年東京都立川市生まれ。
高校3年生の4月に武田塾御茶ノ水本校に入塾し、偏差値31から明治大学商学部へ逆転合格を果たす。大学2年次に英検1級を取得し、イギリスのイースト・アングリア大学に正規留学。その後、一般企業で英語を活用した実務経験を積み、25歳で独立。
現在は、武田塾 練馬校・田無校・ひばりヶ丘校・東久留米校・拝島校・入間校・草津校・滋賀彦根校を統括し、難関国公立・早慶上智・GMARCHなどへの合格者を多数輩出している。また、武田塾のカリキュラム作成に携わりつつ、YouTubeチャンネル「武田塾English」や「武田塾チャンネル」に出演中。
YouTube「武田塾English」では累計400万回再生を突破し、社会人向けの英語学習情報を配信。自身も英語初心者から英検1級やTOEIC990点(満点)を取得した経験をもとに、効率的な英語学習法を広めている。
【取得資格】
・英検1級
・TOEIC 990点
・TOEIC Writing 200点(満点)
・Cambridge英検CPE
【著書】
『Be動詞もわからなかった私が数年でTOEIC満点をとった英語独学法』(幻冬舎)
『大学入試 逆転英単語2000 (武田塾逆転合格一冊逆転プロジェクト) 』(アルク)
推薦入試と総合型選抜(AO入試)の5つの違い!向いている人・後悔しない対策を解説
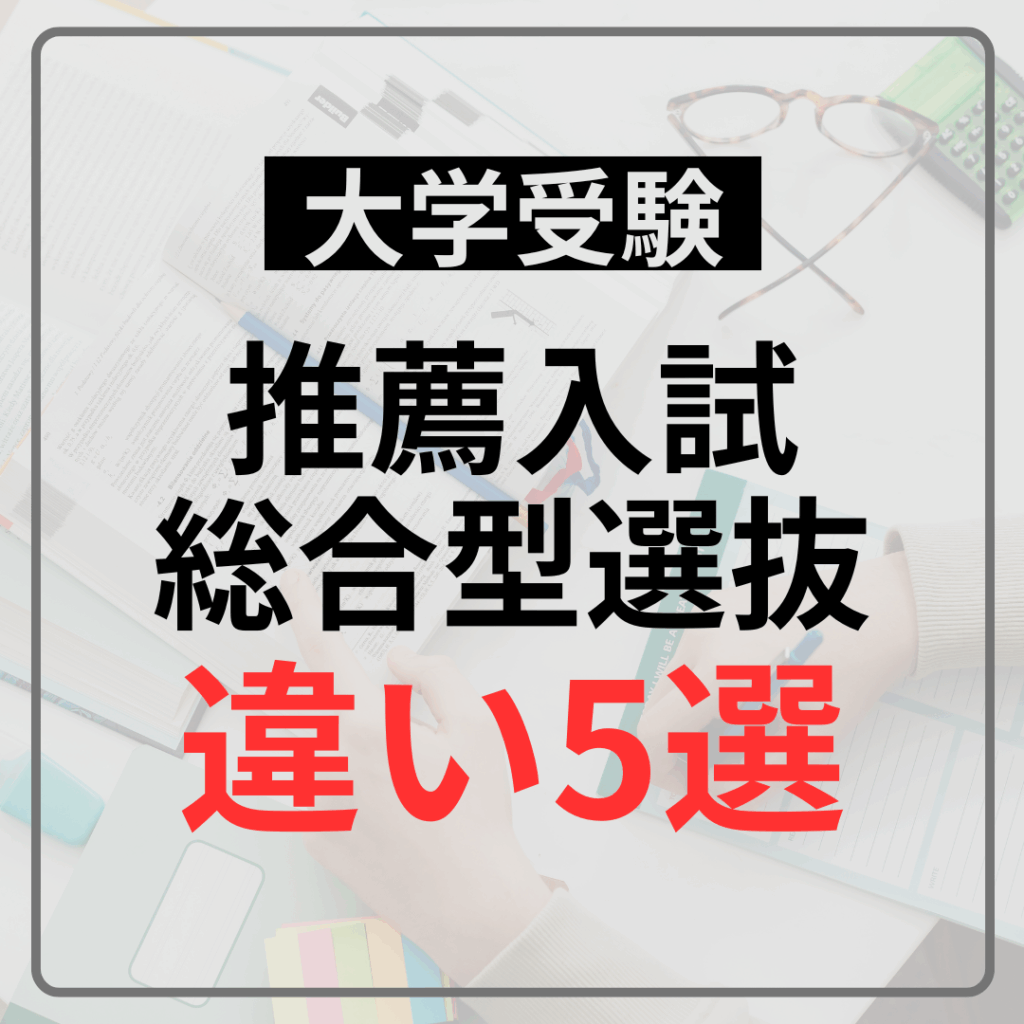
こんにちは!
武田塾で10校舎の統括をしている井関です!
「推薦入試と総合型選抜の違いが知りたい」
「自分の成績で推薦入試を狙えるのか不安」
「総合型選抜はほぼ受かるって本当?」
このように悩んでいませんか?
一般選抜だけでなく、推薦入試や総合型選抜を利用して大学進学を目指す人が増えています。
しかし、それぞれの仕組みや評価基準を理解しないまま受験すると「思っていた入試と違った」「準備が間に合わなかった」と後悔するケースも少なくありません。
そこで本記事では、推薦入試と総合型選抜の違いをはじめ、向いている人や後悔しないための対策を解説します。
自分に合った入試方法を見極めたい方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
推薦入試と総合型選抜(旧AO入試)の仕組みとは?概要をサクッと解説

大学入試にはいくつかの受験方法がありますが、その中でも「推薦入試」と「総合型選抜」は、学力試験だけでは測れない人間性や意欲を評価する入試として注目されています。
どちらも一般選抜よりも早い時期に行われるため、早めの準備が鍵となります。
まずは、まずそれぞれの入試の仕組みを見ていきましょう。
1.推薦入試(学校推薦型選抜)
推薦入試とは「学校推薦型選抜」と呼ばれる入試方式のことです。
高校での学業成績や学校生活の態度など、これまでの取り組みが評価の中心となります。
現在は、国公立大学・私立大学のどちらでも実施されている入試方式です。
推薦入試は、主に指定校制と公募制の2種類に分かれます。
指定校制は、大学が特定の高校を指定して志望者を募集する方式です。
指定された高校の中で、推薦された生徒のみが出願できます。
指定校推薦(指定校制)のデメリット・注意点を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
一方、公募制は大学が示す出願条件(評定平均や出席状況など)を満たし、高校長の推薦を受ければ、どの高校からでも出願できる仕組みです。
どちらの方式でも、書類審査に加えて小論文や面接などが行われます。
2.総合型選抜(旧AO入試)
AOとは「アドミッションズ・オフィス(Admissions Office)」の略です。
各大学や学部が掲げる「アドミッション・ポリシー(求める学生像)」に基づいて、受験生の人物像や意欲を多角的に評価する入試方式が総合型選抜です。
2021年度の大学入試改革により、総合型選抜という名称に変更されました。
名称だけでなく、以下の学力の3要素を総合的に評価する仕組みへと変わっています。
- 知識・技能
- 思考力・判断力・表現力
- 主体性・多様性・協働性
選考方法は大学によって異なりますが、書類審査に加え、小論文や面接、プレゼンテーションなど、さまざまな形式で行われます。
また、総合型選抜は私立大学だけでなく、国公立大学でも実施されており、幅広い受験生にチャンスのある入試制度です。
推薦入試と総合型選抜の5つの違い
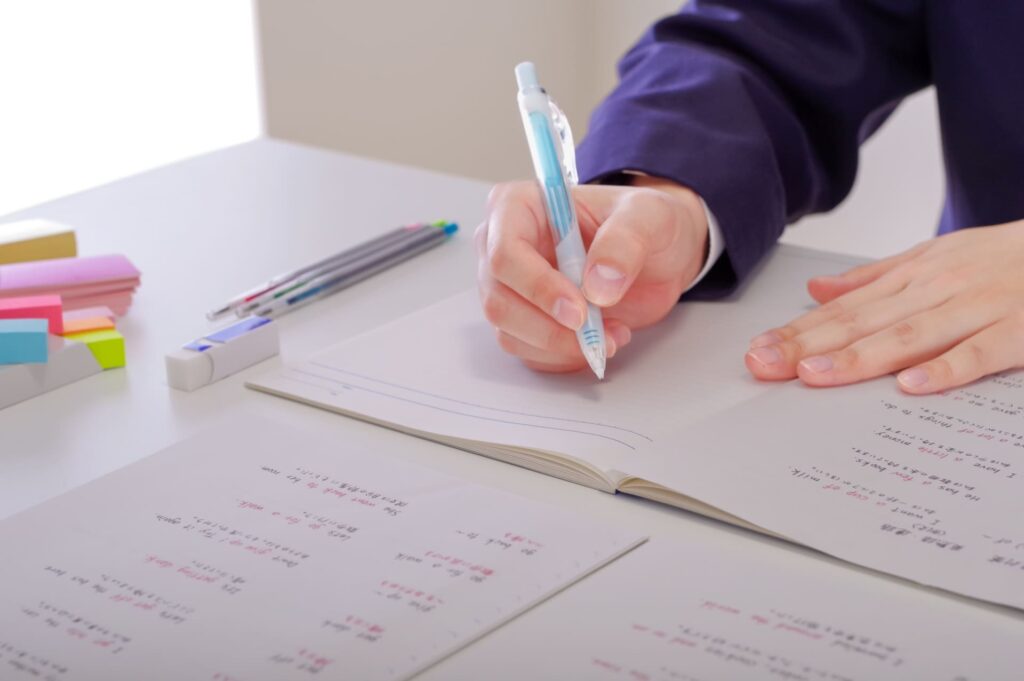
推薦入試と総合型選抜はどちらも似たような制度ですが、以下のような違いがあります。
【推薦入試と総合型選抜の違い】
1.受験資格
2.入試時期
3.選考方法
4.評価基準
5.倍率
どちらが自分に向いているか把握するために、違いを見ていきましょう。
1.受験資格
推薦入試では、出願にあたって学校長の推薦が必要です。
大学があらかじめ公表している出願要件(評定平均や出席状況など)を満たしていても、学校から推薦を受けられなければ出願できません。
校内での成績や生活態度が、重要な判断材料となります。
一方、総合型選抜は学校長の推薦を必要としません。
大学が設定している出願条件を満たせば、誰でもエントリー・出願が可能です。
そのため、総合型選抜の方が多くの受験生にチャンスがある入試方式と言えます。
2.入試時期
推薦入試は、10〜11月頃に出願し、11月下旬〜12月にかけて選考・合格発表が行われるのが一般的です。
ただし、大学や学部によっては、出願・選考の時期がやや遅く、11月〜翌年1〜2月頃に実施されるケースもあります。
一方、総合型選抜は6〜8月頃にエントリーが開始され、9月以降に出願・10〜11月頃に選考・合格発表という流れが一般的です。
大学によっては11〜12月に出願し、12月〜翌年2月に合格発表を行う場合もあります。
どちらの入試も、一般選抜(一般入試)より実施される時期が早いです。
2つの入試方式を比較した場合は、総合型選抜の方が時期が早い傾向にあります。
入試時期は大学ごとに異なるため、各大学の公式サイトや募集要項で確認しておきましょう。
3.選考方法
推薦入試では、書類審査に加えて小論文・面接を中心に選考が行われます。
高校での成績や生活態度など、これまでの努力を重視する傾向があります。
成績だけでなく、日頃の学校生活の姿勢や人柄が評価のポイントです。
一方、総合型選抜では、推薦入試よりも多面的な視点で選考されます。
- 口頭試問
- プレゼンテーション
- グループディスカッション
- フィールドワーク
- 講義レポート
さらに、2021年度の大学入試改革以降は「学力の3要素」も重視されるようになりました。
- 知識、技能
- 思考力、判断力、表現力
- 主体性、多様性、協働性
これらを総合的に評価するため、総合型選抜では学力はもちろん、自分の考えを表現し、他者と協働できる力も問われます。
推薦入試よりも思考力・表現力・主体性を重視した、多面的な評価が行われるのが特徴です。
4.評価基準
推薦入試と総合型選抜では、大学のアドミッション・ポリシー(求める学生像)に合っているかが重視されるという共通点があります。
推薦入試の主な評価基準は、以下のとおりです。
- 推薦入試の主な評価基準
- 評定平均(内申点):高校1~3年の成績
- 出席状況:欠席・遅刻の少なさ
- 人物評価:学校生活での態度、先生からの推薦書
- 面接・小論文:人柄や思考力を確認
高校生活全般での誠実さ、努力の積み重ねが評価の中心となります。
総合型選抜の主な評価基準は、以下のとおりです。
- 評定平均
- アドミッション・ポリシーとの一致度
- 課外活動、実績(部活・ボランティア・コンテストなど)
- 語学力や資格(英検、TOEICなど)
- 面接での熱意やマナー
- 小論文やプレゼン、課題提出
- 実技試験(芸術・スポーツ系など)
総合型選抜では、学校での成績に加えて、主体的な行動・課外活動・探究心なども評価の対象になります。
学力だけでなく、自分の経験や想いをどれだけ大学の学びと結びつけて語れるかが合否を左右するポイントです。
5.倍率
倍率は、総合型選抜よりも推薦入試の方が低い傾向にあります。
推薦入試では、学校からの推薦を得る必要があり、さらに評定平均や出願条件によって受験者数が制限されるためです。
校内で推薦枠が限られている分、出願できる人数が絞られ、結果として倍率が低くなります。
一方で、総合型選抜は出願要件を満たせば誰でも受験できるため、エントリーの自由度が高い入試方式です。
その分、人気の大学や定員が少ない学部では受験者が集中し、倍率が高くなるケースもあります。
大学によって差はありますが、総合型選抜の方が競争が激しくなる傾向が見られます。
推薦入試が向いている人の特徴3選

推薦入試が向いている人の特徴は、以下のとおりです。
【推薦入試が向いている人の特徴】
1.高校の成績(評定平均)が高い
2.出席状況や生活態度が良好
3.進学したい大学や学部が決まっている
推薦入試と総合型選抜どちらが自分に合うか判断する際の参考にしてみてください。
1.高校の成績(評定平均)が高い
高校での成績が高水準で安定しており、評定平均が出願条件を上回る人は、推薦入試に向いています。
推薦入試では、学力試験の点数だけでなく、これまでの高校生活での努力が重視されます。
定期テストの結果や授業態度、提出物など、日々の積み重ねが評価の対象です。
一般選抜のように一度の試験で結果が決まるわけではなく、コツコツと努力を続けてきた人ほど有利です。
多くの大学では評定平均3.5以上を基準としており、難関大学では4.0以上を求められるケースもあります。
普段から授業に真剣に取り組み、安定した成績を維持できていない場合は、校内選考で推薦を得るのが難しくなることに注意しましょう。
2.出席状況や生活態度が良好
欠席や遅刻が少なく、学校生活を真面目に過ごしてきた人も、推薦入試に向いています。
推薦入試では、学業成績だけでなく「日頃の生活態度」も評価の対象となるためです。
授業に取り組む姿勢やクラスでの行動、先生からの信頼なども重要です。
また、推薦入試では無断欠席や遅刻が多いと、校内選考を通過できないこともあります。
一方で、基本的な生活態度をしっかり保っている人は、一般選抜では届きにくい大学でも、合格のチャンスを得られる可能性があります。
3.進学したい大学や学部が決まっている
推薦入試に向いているのは、学びたい大学や学部が明確に決まっている人です。
推薦入試は専願制が基本で、合格後に辞退することは原則として認められていません。
第一志望の大学に対して、強い意思を持っている人ほど適しています。
出願や選考は秋から冬(11月〜12月)にかけて行われ、早ければ年内に進路が確定します。
早期に合格が決まることで、入学後に向けた学習や生活準備に十分な時間を確保可能です。
ただし、明確な志望理由がないまま「合格しやすいから」といった理由で出願すると、入学後にミスマッチを感じて後悔することもあるため注意が必要です。
総合型選抜が向いている人の特徴3選

推薦入試が向いている人と比較できるように、総合型選抜の特徴も見ていきましょう。
【総合型選抜が向いている人の特徴】
1.志望校のアドミッション・ポリシーに合致している
2.アピールできる強みがある
3.探究心があり自己表現できる
それぞれ詳しく解説します。
1.志望校のアドミッション・ポリシーに合致している
総合型選抜は、大学のアドミッション・ポリシーに合致し、学びたい分野を語れる人に向いています。
アドミッション・ポリシーとは、大学が求める学生像のことです。
大学全体や学部・学科ごとに設けられており、総合型選抜における重要な評価基準となっています。
アドミッション・ポリシーに合致している人は、選考において高い評価を得られやすいです。
「なんとなく興味があるから」といった曖昧な動機ではなく、大学や学部の特色を理解し、自分の将来と結びつけて具体的に語るための準備が必要です。
2.アピールできる強みがある
総合型選抜では、アピールできる強みがある人に向いています。
例えば、以下のような実績を強みとしてアピールが可能です。
- 部活動
- ボランティア
- コンテスト
- 資格
総合型選抜では、受験生の個性や人間性も評価対象になります。
自分ならではの経験や個性があり、言葉でしっかりと伝えられる人は、選考の中で評価されやすいです。
また、総合型選抜は、いわば自分という存在を大学にプレゼンする場とも言われています。
「あなたの長所は?」「高校時代に力を入れたことは?」といった質問に対し、自信を持って答えるための準備が大切です。
たとえ実績が華やかでなくても、取り組んできた過程や努力の背景を自分の言葉で表現できる人は、大学側に強い印象を残せるでしょう。
3.探究心があり自己表現できる
総合型選抜に向いているのは「なぜこの大学で学びたいのか」「入学後に何を目指したいのか」といった思いを、論理的かつ熱意を持って表現できる人です。
面接や小論文、プレゼンテーションなどを通して「自分の考えをどれだけ深く、わかりやすく伝えられるか」が評価されるためです。
また、受け身ではなく、自ら課題を見つけて解決しようとする姿勢も評価対象になります。
授業で生まれた疑問を自分で調べたり、文化祭や部活動で主体的に企画・改善に取り組んだ経験があったりする人は、探究心や行動力をアピールできます。
こうした姿勢は、大学での研究やゼミ活動にも直結するため、総合型選抜で高く評価される可能性があります。
推薦入試・総合型選抜で後悔しない3つの対策

推薦入試や総合型選抜は、一般選抜よりも早い時期に動き出す必要があるため、しっかりとした準備が欠かせません。
入試で後悔しないために、以下を意識しましょう。
【推薦入試と総合型選抜で後悔しない対策】
1.早めに志望校を決めて出願条件を確認する
2.学校生活・課外活動の実績を積み上げる
3.志望理由を深めて面接・小論文の対策を始める
全て重要なので、参考にしてみてください。
1.早めに志望校を決めて出願条件を確認する
推薦入試や総合型選抜は、一般選抜に比べて出願の時期が早いため、早めの情報収集と準備が合否を左右します。
特に推薦入試では、評定平均や出席日数といった出願条件があらかじめ大学ごとに定められています。
高校2年生のうちに志望校を絞り込み、条件を確認しておくことが重要です。
条件を満たしていなければ、そもそも出願ができないケースもあるため注意が必要です。
一方で、総合型選抜を実施している大学では、オープンキャンパスへの参加やエントリーが夏前から始まる場合があります。
志望理由書の作成や面接対策など、早い段階から準備が必要になるため、スケジュール管理を徹底しましょう。
「どの大学を受けるか」「どの方式で出願するか」を早めに決めることで、余裕を持って対策に取り組めます。
2.学校生活・課外活動の実績を積み上げる
推薦入試や総合型選抜では、短期間での対策が難しく「これまでどのように過ごしてきたか」という日々の積み重ねが重視されます。
推薦入試では、定期テストの成績や授業態度、学校生活での取り組みなど、校内での評価が重視されます。
一方で総合型選抜では、部活動やボランティア活動、資格取得、探究学習など、学校外での経験や自主的な行動も評価対象です。
そのため、日頃から積極的に活動し、自分の成長を示せるエピソードを増やしておくことが大切です。
授業・部活動・ボランティア・資格取得などを通して、推薦書や志望理由書でアピールできる強みを増やしましょう。
3.志望理由を深めて面接・小論文の対策を始める
どちらの入試でも「なぜその大学で学びたいのか」を自分の言葉で語れるかが重要です。
大学のアドミッション・ポリシー(求める学生像)を理解し、自分がその大学で何を学び、将来どんなことを実現したいのかを明確にしておきましょう。
大学に関心を持ったきっかけや高校時代に取り組んできた経験を整理し、志望理由と結びつけておくのがおすすめです。
事前に確認しておくことで、面接や志望理由書で一貫性のある内容を伝えやすくなります。
また、総合型選抜ではプレゼンやグループディスカッション、小論文が課される場合もあります。
志望分野に関する知識を深めるとともに、自分の考えをわかりやすく伝える練習を重ねておくと、自信を持って臨めるでしょう。
推薦入試・総合型選抜の違い|まとめ

推薦入試と総合型選抜は、一般入試とは異なる形で、自分の力をアピールする入試方式です。
どちらが自分に合っているかを見極めるためには、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。
推薦入試は、学校長の推薦を受けて出願する方式で、高校での学業成績や出席状況など、日々の努力が評価されます。
特に、評定平均が高く、学校生活を誠実に取り組んできた人に向いています。
一方で総合型選抜では、学力試験以外の要素も重視されやすいです。
志望理由書や面接などを通して「自分らしさ」や「大学で学びたい意欲」などが評価されます。
特に、自分の強みや将来の目標をしっかりと表現できる人に適しています。
どちらの入試方式にもメリットがあります。
大切なのは、得意分野や性格、これまでの経験を踏まえて、自分に合った方法を選ぶことです。
早い段階から情報を集め、計画的に準備を進めていけば、合格の可能性を高められるでしょう。
大学受験の対策をするなら武田塾

推薦入試や総合型選抜には、それぞれ合格率の高さや学力以外での評価など、メリットがあります。
しかし「選べる大学が限られる」「評定平均やアピール材料の不足」などの不安要素も存在します。
推薦入試や総合型選抜だけでなく、一般入試といった他の受験方法も含めて、慎重に検討しましょう。
「推薦入試を受けるか、総合型選抜を選ぶべきか迷っている」
「自分の成績で、どの入試方法が合っているのかわからない」
「後悔しない進路選びをしたい」
という悩みを抱えている方は、武田塾の無料相談を利用してみてください。
勉強方法に加えて、受験方法や進路選びなど、どんな些細なことでも相談できる環境が整っています。