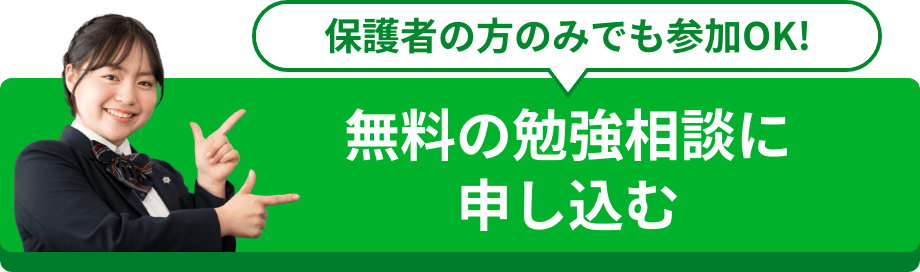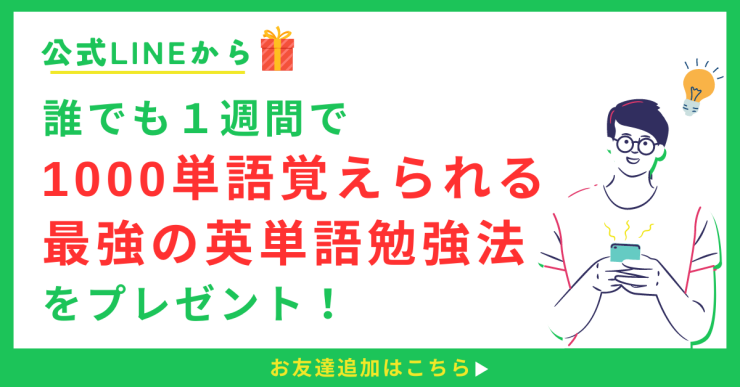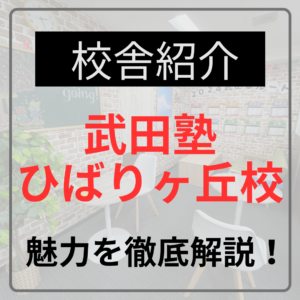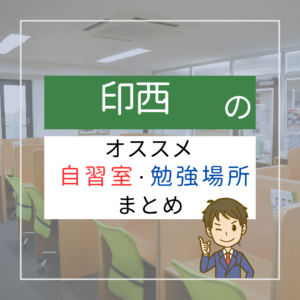武田塾10校舎 統括責任者(練馬校/田無校/ひばりヶ丘校/東久留米校/拝島校/入間校/小山校/草津校/滋賀守山校/滋賀彦根校)
1993年東京都立川市生まれ。
高校3年生の4月に武田塾御茶ノ水本校に入塾し、偏差値31から明治大学商学部へ逆転合格を果たす。大学2年次に英検1級を取得し、イギリスのイースト・アングリア大学に正規留学。その後、一般企業で英語を活用した実務経験を積み、25歳で独立。
現在は、武田塾 練馬校・田無校・ひばりヶ丘校・東久留米校・拝島校・入間校・草津校・滋賀彦根校を統括し、難関国公立・早慶上智・GMARCHなどへの合格者を多数輩出している。また、武田塾のカリキュラム作成に携わりつつ、YouTubeチャンネル「武田塾English」や「武田塾チャンネル」に出演中。
YouTube「武田塾English」では累計400万回再生を突破し、社会人向けの英語学習情報を配信。自身も英語初心者から英検1級やTOEIC990点(満点)を取得した経験をもとに、効率的な英語学習法を広めている。
【取得資格】
・英検1級
・TOEIC 990点
・TOEIC Writing 200点(満点)
・Cambridge英検CPE
【著書】
『Be動詞もわからなかった私が数年でTOEIC満点をとった英語独学法』(幻冬舎)
『大学入試 逆転英単語2000 (武田塾逆転合格一冊逆転プロジェクト) 』(アルク)
指定校推薦のデメリット・やめた方がいい理由8選!後悔しないための4つの対策も紹介
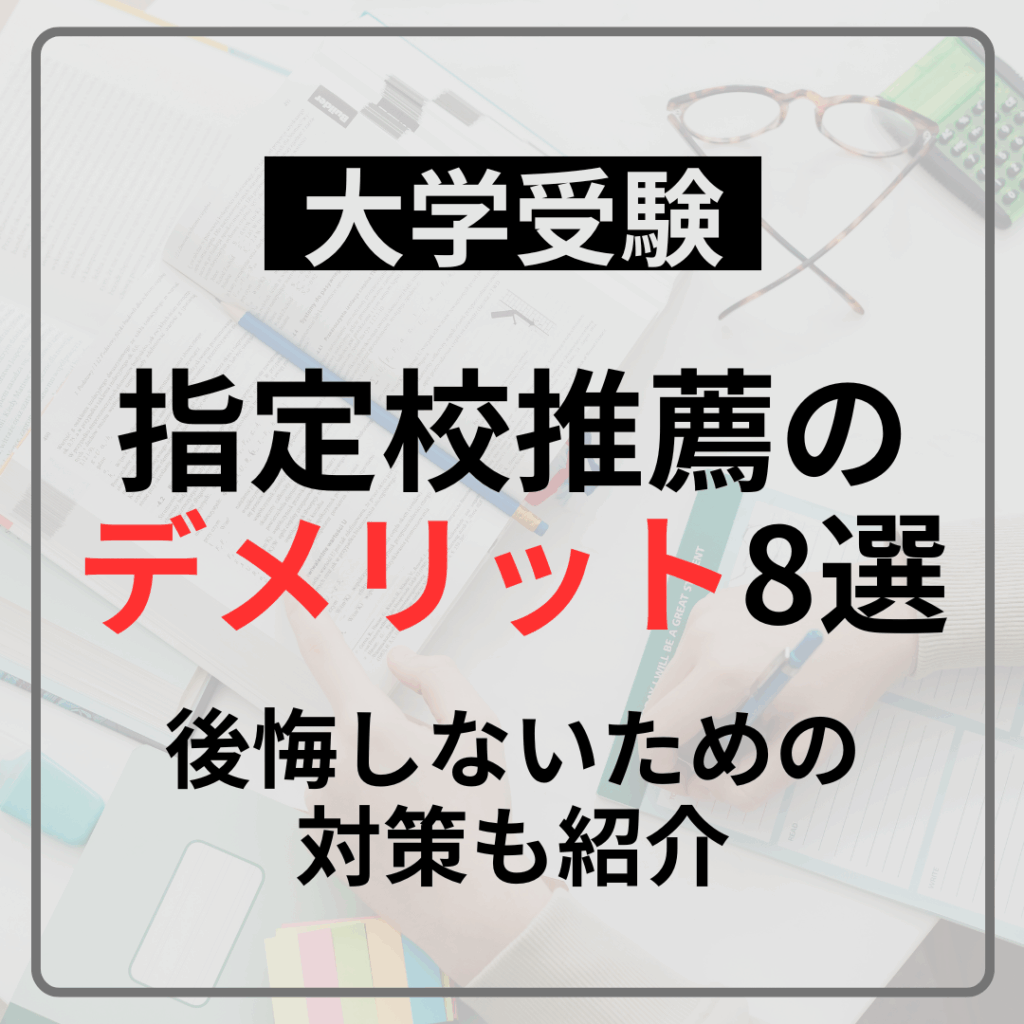
こんにちは!
武田塾で10校舎の統括をしている井関です!
「指定校推薦にはどんなデメリットがある?」
「指定校推薦で合格したら嫌われるって本当?」
「向いている人・向いていない人を知りたい」
このように悩んでいませんか?
指定校推薦は、利用者の多い入試制度の一つです。
しかし、いくつかのデメリットがあるため、制度を理解しないまま利用すると、進路選びで後悔する可能性があります。
そこで本記事では、指定校推薦のデメリットをはじめ、メリットや向いている人・向いていない人などを解説します。
指定校推薦を利用するか迷っている方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
指定校推薦とは?概要をさくっと解説

指定校推薦は、日本の大学入試制度の一つで「学校推薦型選抜」に含まれる入試方式です。
大学が定める高校での成績基準を満たした生徒の中から、希望者が学内で選考されます。
一般入試のように学力試験の結果だけで判断されるのではなく、評定平均や出席状況など、高校での取り組みが選考基準として重視されるのが特徴です。
高校側は大学が設定した基準を踏まえて、条件を満たした生徒を選び、推薦書を提出します。
選考内容は大学によって異なり、推薦書の提出だけでなく、面接・小論文・学科試験などが課される場合もあります。
推薦入試と総合型選抜(AO入試)の違いも合わせて知りたい方はこちら👇
指定校推薦のデメリット・やめた方がいい理由8選

指定校推薦には、さまざまなメリットがありますが、デメリットも存在します。
理解しないまま受験を決めると、後悔につながる可能性があるので注意しましょう。
指定校推薦のデメリットは、以下のとおりです。
【指定校推薦のデメリット】
1.指定校推薦枠がなければ受験できない
2.競争率が高い
3.他大学との併願ができない
4.合格後の辞退や中途退学が難しい
5.国公立大学では実施されていない
6.入学後に学習面で苦労する可能性がある
7.志望校を妥協するケースがある
8.周囲の目や人間関係に影響することもある
どれも大切なポイントなので、ここでしっかり確認しておきましょう。
1.指定校推薦枠がなければ受験できない
指定校推薦は、大学によって特定の高校へ推薦枠が割り当てられる仕組みです。
どの高校からでも、自由に出願できるわけではありません。
そのため、自分が進学したい大学の推薦枠が設けられていなければ、そもそも指定校推薦での受験は不可能です。
「志望校の指定校推薦枠があるか」は高校によって異なるため、必ずしもチャンスがあるとは限りません。
指定校推薦を検討している場合は、早めに高校の先生に相談して確認しておきましょう。
2.競争率が高い
指定校推薦は、人気大学や人気学部ほど枠が限られており、数名しか割り当てられないケースが多くあります。
そのため、校内での競争率が高くなるのが現実です。
選考に漏れてしまうと、指定校推薦は利用できません。
推薦を受けられるかは、評定平均・授業態度・出席状況などを基に、総合的に評価されます。
特に評定平均は重要で、校内選考を突破するには4.0以上が求められるケースが多いです。
また、部活動や委員会活動などでの実績が加点要素になることもあります。
苦手科目が足を引っ張って基準に届かない場合や、遅刻・欠席が多い場合は注意が必要です。
基準を満たせず、推薦対象から外れる可能性が高まります。
指定校推薦を狙うなら、日頃から学習態度や生活態度を整えておくことが欠かせません。
3.他大学との併願ができない
指定校推薦は専願制が基本です。
一度合格が決まれば、その大学に入学しなければならず、他大学との併願はできません。
合格後に「やっぱり別の大学を受けたい」と考えても後戻りはできず、軽い気持ちで出願すると後悔につながることがあります。
指定校推薦を利用する際は「その大学で本当に学びたいか」「将来につながるか」をよく考え、慎重に判断しましょう。
4.合格後の辞退や中途退学が難しい
指定校推薦での合格は、高校を代表してその大学に進学するという意味を持ちます。
合格が決まった後は、原則として辞退できません。
また、入学してから「思っていた大学生活と違った」と感じても、進路を変更することは難しいです。
中退すすると、出身高校の今後の推薦枠に悪影響を与える可能性があります。
そのため、指定校推薦を希望する前に「本当にその大学に卒業まで通い続けられるか」を考えることが重要です。
5.国公立大学では実施されていない
指定校推薦は、基本的に私立大学が中心の制度です。
国公立大学を志望する場合には利用できず、進路の選択肢が限られてしまいます。
国公立大学を目指すのであれば、一般選抜や学校推薦型選抜(公募制)といった、別の入試方式で合格を目指す必要があります。
志望校が国公立大学の場合、指定校推薦が選択肢に入らないため、早い段階から自分に合う受験方式を意識した準備が大切です。
6.入学後に学習面で苦労する可能性がある
指定校推薦で合格した場合、一般入試組と比べて学力の差を感じるケースがあります。
合否は12月頃と早い時期に決まり、受験勉強から解放されます。
結果として、一般入試を利用する人よりも学習が疎かになる人もいるのです。
さらに、指定校推薦は学力試験だけで判断される方式ではありません。
入学後に「授業についていけない」「周囲のレベルの高さに焦る」といった不安やストレスを抱えるケースがあります。
そのため、合格後も学習を継続し、大学の授業に備えて基礎力を固めておくことが重要です。
7.志望校を妥協するケースがある
指定校推薦の枠は、すべての大学に設けられているわけではありません。
志望校の推薦枠がない場合は、別の大学を選ぶことになるケースもあります。
また「一般入試は受けたくない」「早く受験を終わらせたい」といった理由から、第一志望ではない大学を選ぶ人もいます。
妥協した結果、入学後に「やっぱり別の大学に行きたかった」という後悔につながることもあるでしょう。
指定校推薦を利用する際は「本当に通いたい大学かどうか」を見極めることが大切です。
8.周囲の目や人間関係に影響することもある
指定校推薦は合否が早く決まるため、一般選抜を受ける同級生から「楽をして合格した」と思われることがあります。
中には、嫉妬されたり嫌味を言われたりするケースもあります。
また、指定校推薦を取れなかった友人との関係がぎくしゃくし、ストレスを感じる人もいるでしょう。
友人とのわだかまりは、時間が経てば落ち着くことが多いです。
しかし、合格直後は周囲との温度差に悩む可能性がある点は、知っておきましょう。
指定校推薦はデメリットばかりではない!5つのメリット

指定校推薦にはデメリットもありますが、悪い面ばかりではありません。
実際には、以下のようにさまざまなメリットがあります。
【指定校推薦のメリット】
1.合格率が高い
2.早い段階で進路が決まる
3.学力以上の大学に進学できる
4.受験の精神的負担を減らせる
5.受験にかかる費用を抑えられる
正しく理解するために、メリットも把握しておきましょう。
1.合格率が高い
大学が定める成績基準を満たしたうえで、校内で選抜された生徒が利用できる入試方式のため、合格率が高いのが特徴です。
高校から推薦を受けた時点で、大学側から一定の信頼が保証されていると言えます。
その結果、一般入試に比べて合格までのハードルが低く、安心して進められるのが特徴です。
専願制であるため「この大学に行きたい」という強い気持ちがある人は、合格率が高い指定校推薦の利用を検討しましょう。
2.早い段階で進路が決まる
指定校推薦は多くの場合、秋頃に選考が行われ、年内には合否が判明します。
合格すれば、一般入試を受ける人よりも早く受験勉強から解放され、精神的にも余裕が生まれます。
指定校推薦の合否は、3年間の評定平均によって大きく左右されるため、早めから学習を頑張ってきた人にとって有利な制度です。
高い成績を維持できており、早い段階で進路を決めたい場合は、高校の先生に相談してみましょう。
3.学力以上の大学に進学できる
指定校推薦を利用することで、一般入試では手が届かない大学にも挑戦できる可能性があります。
校内での成績や生活態度が評価されるため、学力試験での一発勝負が苦手な人でも有利に働くケースがあるのです。
推薦の判断基準は、評定平均や出席状況といった日頃の取り組みが中心です。
試験内容も、面接や小論文など人物面を重視する傾向があります。
指定校推薦で合格すれば、受験勉強から早く解放されます。
一方で、入学後に学習面で苦労する可能性もあるので、自由に使える時間を活用して準備をすることが大切です。
4.受験の精神的負担を減らせる
指定校推薦は、一般入試と比べて受験の競争倍率が低く、合格の可能性が高いのが特徴です。
そのため「受かるかわからない」というプレッシャーを軽減できます。
早い段階で合格が決まれば、残りの高校生活を落ち着いて過ごせるのもメリットです。
また、入学に向けて余裕をもって準備を進められるのも魅力です。
5.受験にかかる費用を抑えられる
一般入試では複数の大学を併願するケースが多く、そのたびに受験料や交通費、宿泊費といった費用がかかります。
受験校が増えるほど負担も大きくなり、大きな出費となることもあるでしょう。
一方で、指定校推薦は専願制のため、受験回数は少なく済みます。
その分、受験にかかる費用を大幅に抑えられるのもメリットです。
経済的な負担を減らしたい家庭にとっても、指定校推薦は魅力的な選択肢と言えます。
指定校推薦で後悔しないための4つの対策

指定校推薦について正しく理解して準備をしないと「もっと勉強しておけばよかった」「別の大学にすればよかった」といった後悔につながります。
失敗を防ぐために、以下のポイントを押さえておきましょう。
【指定校推薦で後悔しない対策】
1.日頃から学習をして高い成績を維持する
2.学校活動や外部試験に積極的に取り組む
3.先生とコミュニケーションを取る
4.自分に合う進路を考える
それぞれ参考にしてみてください。
1.日頃から学習をして高い成績を維持する
評定平均が合否を大きく左右するため、定期テストで高得点を維持する必要があります。
短期的な詰め込み勉強をするのではなく、1年生の頃から能動的に学習し、定着させることが重要です。
学習習慣を身につけたい場合は、塾に通うことも検討しましょう。
塾に通うことで学習リズムを作れて、高い成績を維持しやすくなります。
学校の授業の補強や定期テスト対策ができるため、指定校推薦を目指す人にとって有効な手段となり得ます。
2.学校活動や外部試験に積極的に取り組む
指定校推薦では、成績だけでなく学校生活全体での取り組みも評価対象です。
部活動や生徒会、ボランティア活動などに積極的に参加することで、推薦書に記載されるアピールポイントが増えます。
さらに、英検や漢検といった外部試験に挑戦しておくと、資格として評価されます。
面接や小論文で「努力してきた証」として、強みを示すことも可能です。
勉強と並行して学校活動や外部試験に取り組むことで、評価されやすくなり、合格の可能性を高められます。
3.先生とコミュニケーションを取る
指定校推薦を受けるには、校内選考を突破する必要があります。
普段から授業態度を意識したり、提出物の期限を守ったりして、先生との信頼関係を築いておくことが大切です。
また、推薦枠の有無や校内選考の基準といった重要な情報は、先生から得られます。
指定校推薦を検討している場合は、担任や進路指導の先生に相談しておくと安心です。
早めに動くことで、必要な準備や自分に足りない点が明確になり、合格に向けた対策を立てやすくなります。
4.自分に合う進路を考える
指定校推薦は専願制であるため、合格した時点でその大学に進学することになります。
軽い気持ちで出願してしまうと「やっぱり別の大学に行きたかった」という後悔につながりやすい点に注意が必要です。
後悔を避けるためには「大学で何を学びたいのか」「将来どのような仕事に就きたいのか」を明確にし、自分に合った進路を考えることが大切です。
先生への相談に加えて、学習塾での進路相談を活用することで、より客観的な視点からアドバイスしてもらえます。
指定校推薦の受験でよくある質問

指定校推薦の利用を実際に考えると、さまざまな疑問や不安が出てくるものです。
ここでは、よくある質問に回答していきます。
【指定校推薦の受験でよくある質問】
1.一般入試で合格した人に嫌われますか?
2.総合型選抜(AO入試)とどっちが良いですか?
3.就職で不利になりますか?
事前に不安を解消し、自分に合った受験方法を決める際の参考にしてみてください。
1.一般入試で合格した人に嫌われますか?
結論から言えば、指定校推薦を利用したからといって、嫌われることはありません。
入学直後は、受験方法の話題になることもあるでしょう。
しかし、時間が経てば誰がどの入試方式で入学したかを意識する人は、ほとんどいなくなります。
また、大学には指定校推薦のほかにも、付属高校からの内部進学や総合型選抜(AO入試)など、さまざまな入試ルートで入学してきた学生がいます。
実際の大学生活では、受験方式は大きな問題にならないので、嫌われることを心配して指定校推薦を避ける必要はありません。
2.総合型選抜(AO入試)とどっちが良いですか?
指定校推薦と総合型選抜は、どちらも「一般入試以外の方法」に分類されます。
指定校推薦は、校内選考を突破できれば、合格率が高いことが特徴です。
合否の判定では、評定平均や生活態度など、日頃の学校生活が重視されます。
専願制であるため、進路を一本に絞る覚悟が求められます。
指定校推薦が向いている人は、以下のとおりです。
- 入学したい大学が決まっている(指定校推薦の枠がある)
- 高校1年生から高い成績を維持している
- 学校での生活態度が良い
- 先生と円滑にコミュニケーションを取れている
一方で、総合型選抜(AO入試)では、自分の適性や意欲など、多様な要素を総合的に評価されます。
面接や小論文を通じて、自分の強みや将来の目標をどれだけ表現できるかが鍵となります。
総合型選抜が向いているのは、以下のような人です。
- 大学のアドミッションポリシーに合致している
- 将来やりたいことが明確になっている
- 自分の強みや個性を表現できる
- 課外活動や資格取得の実績がある
どちらが良いかは「志望校の推薦枠があるか」「高校での成績が安定しているか」などによって変わります。
後悔しないように、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。
3.就職で不利になりますか?
指定校推薦で大学に入学したことが、就職活動で不利に働くことはありません。
入試方式で判断されることはなく、大学での学びや経験などが重視されます。
また、インターンシップやゼミ活動など、大学生活の中で得た実績や取り組みも評価対象になります。
指定校推薦で合格すると、早い段階で進路が決まるため、大学入学前から余裕を持って準備できるのがメリットです。
大学で何をするかを明確にして行動できれば、就職活動でも自信を持ってアピールできる材料を作りやすいです。
指定校推薦のデメリット|まとめ

指定校推薦は専願制で他大学を受験できなかったり、入学後に勉強についていけない不安があったりと、いくつかのデメリットも存在します。
さらに「推薦枠が少なく校内選考が厳しい」「合格後に辞退できない」など、受験前にしっかり理解しておくべき注意点も多い制度です。
一方で「合格率が高い」「早く進路が決まる」といったメリットもあります。
自分の状況を踏まえ、指定校推薦が本当に向いているのかを見極め、後悔のない選択をしましょう。
大学受験の対策をするなら武田塾

指定校推薦には合格率の高さなどのメリットがある一方で「専願で他の大学を受けられない」「入学後に勉強についていけるか不安」といったデメリットもあります。
だからこそ、一般入試や総合型選抜など、他の選択肢も検討しておくことが大切です。
「指定校推薦にするか、一般入試で挑戦するか迷っている」
「今の評定で推薦を狙えるのか不安」
「後悔しない大学選びをしたい」
という悩みを持つ方は、武田塾の無料相談を活用してみてください。
勉強方法だけでなく、受験方式や進路選びなど、どんな些細なことでも相談できます。
指定校推薦のデメリットを正しく理解しつつ、自分に合った受験方法を一緒に考えていきましょう。